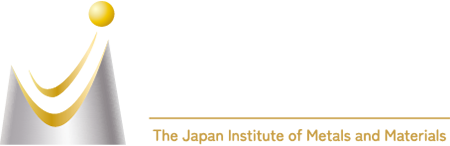- HOME
- 各種賞:日本金属学会各種賞の概要
- 金属組織写真賞
- 第75回(2025年)
金属組織写真賞
第75回金属組織写真賞 選評
本年度の応募件数は、「1. 光学顕微鏡部門」は2件、「2. 走査電子顕微鏡部門」3件、「3. 透過電子顕微鏡部門」1件、および「4. 顕微鏡関連部門」3件の計9件であった。
選考委員会での事前評価結果を理事会において報告し、金属組織写真賞規則に従って、最優秀賞1件、優秀賞2件、ならびに奨励賞2件の授賞を決定した。
今回もWeb審査を踏襲し、選考委員19名に順位点と評価点(5点満点)、および評価の高い作品については選定理由の記載をお願いした。部門も含めた内訳としては、透過電子顕微鏡部門から最優秀賞1件、光学顕微鏡関連部門と走査電子顕微鏡部門からそれぞれ優秀賞1件、および走査電子顕微鏡部門と顕微鏡関連部門からからそれぞれ奨励賞1件となった。
最優秀賞「In2Te3結晶中の原子空孔の秩序配列と180度ドメイン形成」(3. 透過電子顕微鏡部門)は、カチオン(In)とアニオン(Te)の原子識別と構造空孔分布の可視化に成功し、ドメイン内部がIn原子(もしくは構造空孔)の占有率と結晶方位が<001>方位に沿って徐々に変化する構造傾斜領域から成ること、およびドメイン中央部を境に極性が反転するナノ構造を取ることを明らかにした研究である。これまでの常識を覆し、最先端の電子顕微鏡技術を用いて新たなドメイン壁の局所構造を解明した点が、学術的に高く評価された。
優秀賞(部門別、受付番号順)1件目「蛍光イメージングを用いたモデル材料の凝固過程のその場観察」(1. 光学顕微鏡部門)は、レーザー共焦点蛍光顕微鏡を用いた凝固プロセス観察で、従来手法では困難であったミクロ偏析の定量評価を実現した点が革新的と判断された。また蛍光イメージング法を凝固研究に応用する新規性とその技術的な完成度も大きく評価された。優秀賞2件目「Ti-Fe花状共晶組織を利用した、キンク帯強化「ミルフィーユ条件」の解明」(2. 走査電子顕微鏡部門)では、花状共晶組織を利用し層状にひずみ分布を与えることでキンクを導入する「拡張ミルフィーユ制御」という新概念を実証した点が、その波及効果も含め、学術的に高く評価された。
奨励賞「粒界を跨ぐ塑性すべり」(2. 走査電子顕微鏡部門)では、粒界を跨ぐ塑性すべりのメカニズムを詳細に観察し、特に粒界での転位の堆積とその後の塑性すべりの発生を実験的に解明した研究である。金属材料の加工硬化メカニズムの理解を深めるだけでなく、結晶塑性構成式の基礎データとしても重要な貢献と判断された。奨励賞2件目「フェーズフィールドモデルに基づく画像処理によって実現された高速4D-CT観察」(4. 顕微鏡関連部門)は、時間分解X線トモグラフィー(4D-CT)における時間分解能の追求に伴う再構成像の劣化を、フェーズフィールドモデルに基づく画像処理を通じて復元した研究である。凝固現象の実証的理解や理論体系の構築などへの学術的波及効果が大きいと判断された。
惜しくも選に漏れた作品も含め今回もレベルの高い力作揃いであった。他の学会に例を見ない独自性と学術性を重んじてきた金属組織写真賞の継続と発展のため、今後もますます優れた金属・材料の組織写真が応募され続けることを期待したい。
金属組織写真賞委員会委員長
小山 敏幸(名古屋大学)
| 受賞結果 | 最優秀賞 1件 優秀賞 2件 奨励賞 2件 |
|---|---|
| 応募作品数 | 【第1部門】 2件 【第2部門】 3件 【第3部門】 1件 【第4部門】 3件 |
最優秀賞
In2Te3結晶中の原子空孔の秩序配列と180度ドメイン形成
応募部門
3.透過電子顕微鏡部門
応募者・共同研究者
1. 齋藤 嘉一, 秋田大学
2. 早坂 祐一郎, 東北大学
3. 平賀 贒二, 東北大学
作品の説明
熱電変換素子の高性能化に向け、そこで使用する熱電材料が具備すべき条件として、大きな熱起電力を有し、電気抵抗は小さく、かつ熱を逃がさないために熱伝導が小さいこと等が基本要件とされる。本研究で注目するⅢ2Ⅵ3化合物半導体は、Ⅲ族元素としてGaまたはIn、Ⅵ族元素としてSeまたはTeの組み合わせから成り、次世代の熱電材料候補として有望視されている。一般に、Ⅲ2Ⅵ3結晶として複数の構造多形の存在が知られる中で、代表的な構造は共有結合性の正四面体ブロックを基本とする閃亜鉛鉱型構造である。このとき、分子式中のカチオン(Ga3+ or In3+)とアニオン(Te2- or Se2-)の比は2:3であるにもかかわらず、単位胞中の各格子点数比は1:1であることから、理論上はカチオンサイトの3分の1が原子空孔(Vacancy)となる。この化合物中の空孔は結晶の電気的中性を保つうえで必須なもので、結晶構造の安定化に重要な役割を担うことから、普通の空孔と区別して構造空孔と呼ばれる。先行研究によれば、Ⅲ2Ⅵ3結晶の多くは600~700°Cの温度範囲内で構造相転移を起こし、特に高温相はナノスケールの界面を伴って分域化する例が1990年代に行われた電顕観察を通じて広く認められるようになった。さらに2010年前後、高温相の熱伝導率が低温相に比べて顕著に低減する例が相次いで報告され、これを契機にⅢ2Ⅵ3半導体の構造物性に関して以下の解釈が定着する。
1) 結晶中に多量に存在する構造空孔が二次元的に集合して空孔面({111}面)を形成し、これがドメイン壁を構成する。
2) 材料中にナノスケール間隔で配列した{111}空孔面が熱フォノン散乱に対する有効な結晶界面として機能し、ひいてはバルク熱伝導率の低減に寄与する。
一方、筆者等は定説1)、2)について長年にわたり疑念を抱いてきた。事実、通常の高分解能電子顕微鏡法の性能では、原子空孔の所在はおろか、結晶中のカチオンとアニオンの各原子を区別して観察することは不可能と言ってよい。こうして、従来の構造解析結果をはじめ、これに基づく熱伝導影響に関する学説は、根拠のない憶測に過ぎないものとして容認できなかった。以上を動機として、最近筆者等のグループではIn2Te3結晶の高温相(650℃時効材;β-In2Te3)を例に、これまでに試されたことのなかった最新の電子顕微鏡技術、つまり球面収差補正機能付きの走査透過型電子顕微鏡法(Cs-STEM/EDXS)の適用を試みたところ、果たしてカチオン(In)とアニオン(Te)の原子識別と構造空孔分布の可視化に成功し、従来説を覆すナノ構造の実態が明らかになった。つまり、
a) β-In2Te3結晶中のドメイン境界は、閃亜鉛鉱型構造(a = 0.6153 nm; F-43m)の{111}副格子面に相当する180度ドメイン壁から成り、これを境に隣接ドメイン間で結晶構造の極性は反転する (Fig. 1)。
b) 構造空孔が一部の{111}面に集合してドメイン壁を構成するとの従来解釈は誤りである。構造空孔はドメイン内部のInサイトに不規則に分布するが、一定の空間的秩序を有する。これを受けて、ドメイン内部はIn原子(もしくは構造空孔)の占有率と結晶方位が<001>方位に沿って徐々に変化する構造傾斜領域から成り、ドメイン中央部を境に極性は反転する (Fig. 2)。
このような構造空孔の自己組織化ともいえる現象が関与したドメイン形成の観察は過去に前例がなく、Ⅲ2Ⅵ3化合物半導体の学理を追究するうえで重要な発見となった。
学術的価値
β-In2Te3母相に対し,Cs-STEMを利用して[110]方位からHAADF-STEM像を求めると、InとTeの各原子カラムに相当する2つの輝点が対を成してFCC格子を構成する様子が識別できるようになるが、特にIn輝点の強度は当該原子カラム内に存在するIn原子と原子空孔の割合に依存して決まると考えられる。本作品の学術的価値は、以上のアプローチを利用して従来説を覆す原子空孔配列の特徴をはじめ、ドメイン壁の局所構造を解明した点にある。
技術的価値
TEM/STEMを利用した原子識別画像の収集技術が普及して久しいが、一方で元素識別や原子空孔分布の定量解析に耐える画像データを得ることは未だ技術的に難関な作業である。本作品の画像は,結晶中のカチオン(In)とアニオン(Te)の元素識別と各原子サイトにおける占有率変化、ひいては構造空孔分布の定量解析までを可能にする情報を含むデータとして、その収集に係る技術的価値は高い。
組織写真の価値
本作品の中倍率像(Fig.1(a)、Fig.2(a))によると、ドメイン形成に係る組織学的情報に富む点に高い価値を有し、例えば、ドメイン形状やサイズ、ドメイン壁の分散状態、壁密度などのパラメータの特定・推定をはじめ、母相[110]方向に平行な原子コラムに相当する輝点コントラストの特徴を頼りに、単一ドメイン内における結晶構造の極性方向とその変化(図中の矢印)の様子までを知ることができる。
材料名
真空溶解によって得た高純度In2Te3母合金(99.99%以上)を元に、石英管中に真空封入し、一旦1000℃の加熱により溶解した後、650℃一定下で72時間の時効処理を行ったものを観察試料に供した。
試料作製法
前述のIn2Te3合金の650℃時効材に対し、乳鉢を用いた粉砕によって得た薄片をSTEM観察に供した。
観察手法
球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 (Titan³ 60-300 Double Corrector equipped with Super-X EDS system) を使用し、加速電圧200kVの下でHAADF-STEM像(収束角:18 mrad、取り込み角:79-200 mrad)ならびにEDXSマッピング像を取得した。
出典:Kaichi Saito, Yuichiro Hayasaka, Kenji Hiraga, Phys. Rev. B, 184 (2024) 184110.
優秀賞
蛍光イメージングを用いたモデル材料の凝固過程のその場観察
応募部門
1. 光学顕微鏡部門
応募者・共同研究者
1. 川西 咲子, 京都大学
2. 塚原 優希, 東北大学
3. 中尾 温斗, 京都大学
4. 寺島 慎吾, 東北大学
5. 助永 壮平, 東北大学
6. 江阪 久雄, 大阪大学
7. 柴田 浩幸, 東北大学
作品の説明
本作品は光学顕微鏡の一種であるレーザー共焦点蛍光顕微鏡を用いた凝固プロセスのその場観察像である。溶融合金の凝固過程を模擬可能な透明有機材料は、光学顕微鏡を用いて凝固界面形状をその場観察できることから、古くから凝固現象の解明に重宝されてきた。このようなモデル材料を用いた凝固過程のその場観察時に、界面形状に加えミクロ偏析の挙動を評価する新規な手法として、応募者らはレーザー共焦点蛍光顕微鏡を用いた溶質濃度分布の蛍光イメージング法を開発した。本手法では、代表的なモデル材料であるサクシノニトリルを溶媒とし、蛍光試薬であるルモゲンイエローと水を溶質とする三元系を用い、図1に模式図を示すようにデンドライト成長の進行過程のその場観察を行う。図2はその場観察により得られた溶質濃度分布のカラーマップであり、ミクロ偏析により生じた液相中でのルモゲンイエローの濃度分布を蛍光強度(図中の挿入画像)を基に定量評価したものである。加えて、図3に示すように、高さ方向のスタック画像よりデンドライトの三次元形状の可視化にも成功した。その結果、試料全体に占める固相の割合の定量評価が可能になり、デンドライトの発達によるミクロ偏析の進行過程を、溶質の平衡分配と溶質の拡散現象による凝固モデルを用いて説明できることが明らかになった。さらに、図4(a)に示すように、ミクロ偏析の進行によりルモゲンイエローが液相中で過飽和となった際に、図中矢印の箇所にて1um程度のサイズのルモゲンイエローが晶出する様子が捉えられた。この過飽和は、ミクロ偏析によるルモゲンイエロー自身の濃化だけでなく、水の濃化および凝固温度の低下によるルモゲンイエロー溶解度の低下という複合的な要因の結果生じたものである。本晶出現象は、溶融合金の凝固過程においてミクロ偏析に由来して介在物が晶出するのと同じ原理であり、モデル材料を用いてその挙動を再現することができた。図4(b)では介在物の成長および新たな晶出が捉えられており、時間とともに増加する介在物の数密度より、介在物の晶出頻度を評価するに至った。晶出頻度は過飽和条件に大きく依存して変動し、古典的核生成理論に従って介在物の晶出を生じたことが明らかになっている。
学術的価値
生物分野で活用される蛍光イメージング法を世界に先駆けて凝固研究に導入し、ミクロ偏析をその場観察により定量評価する手法を確立した。さらに、モデル材料を用いた凝固過程において、デンドライトの三次元形状の取得や、介在物晶出過程のその場観察にも成功した。凝固後の製品の良し悪しを大きく左右する偏析や介在物の制御に向け、凝固プロセスを基礎から理解することに繋がることから、高い学術的価値を有する。
技術的価値
種々の蛍光試薬を検討し、蛍光強度や溶解度の温度・組成依存性を基に、独自の最適な試料系に辿り着いたことで、ミクロ偏析の定量評価および介在物の晶出過程のその場観察が可能になった。加えて、スピニングディスク式の共焦点系による観察方式を採用したことで、微弱な蛍光でも露光時間50msの短時間での撮影が可能となり、凝固時の動的な挙動を高精度に把握するに至った。
組織写真の価値
デンドライトの先端近傍における溶質濃度分布には議論の余地があり、一次アーム間での溶質濃度が沖合から中心に向け直線的に増加すると仮定されることもあった。本組織写真では、溶質濃度分布の定量評価が可能になったことで、一次アーム間にてカーブを描くように溶質濃度が上昇することが実測から明らかになった。介在物の晶出過程の組織写真も含め、その場観察によるプロセスの解明へと繋がる価値を有する。
材料名
サクシノニトリル-水-ルモゲンイエロー
試料作製法
精製したサクシノニトリルに所定量の水およびルモゲンイエローを添加し、80℃にて均一な溶液を作製した。160mm×26mmサイズの薄いガラスセル内にこの溶液を80℃に保持した状態で封入し、溶液厚み150umの試料を得た。
観察手法
温度勾配を付与したステージ上で試料セルを一定速度で移動してデンドライト成長を促した。レーザー共焦点蛍光顕微鏡を用いて、凝固過程の試料からの蛍光を高感度eCMOSカメラを用いて撮影し、その場観察を行った。
出典:川西咲子, 寺島慎吾, 塚原優希, 助永壮平, 江阪久雄, 柴田浩幸: 鉄と鋼, (2024) 早期公開.
優秀賞
Ti-Fe花状共晶組織を利用した、キンク帯強化「ミルフィーユ条件」の解明
応募部門
2.走査電子顕微鏡部門
応募者・共同研究者
1. 萩原 幸司, 名古屋工業大学
2. 徳永 透子, 名古屋工業大学
3. 米村 拓哉, 名古屋工業大学
作品の説明
本作品は新規耐熱材料として期待されるTi-Fe二元合金における特徴的な「花状共晶組織」(申請者らが命名)に着目することで、これまで詳細が解明できなかった、複相合金においてキンク変形帯の形成によりキンク強化を生じる「ミルフィーユ条件」に対する理解を劇的に進展させた意義深い実験結果を示すものである。
キンク帯は活動する転位がすべり面に対し垂直に配列することで形成するもので、近年Mg合金の強度を大きく向上する新たな機構(キンク強化機構)を担う因子として大変注目されている。この「キンク帯形成に伴う材料強化」を実現する条件は、2022年度まで実施された新学術領域研究「ミルフィーユ構造の材料科学」にて「ミルフィーユ条件」という名称のもと、その解明が進められてきた。
キンク帯を形成するには、材料中で活動するすべり系を一つに限定する必要があり、その実現には複相材料においては、硬質相と軟質層が「交互積層」することが重要ではないか、と推察されていた(これが、軟質なクリームと硬質なパイ生地の積み重ねに例えたミルフィーユ構造という名称の由来である。)しかし、両相の間に幾何学的条件は必要なのか?また「交互積層」する組織は板状でないとダメなのか?といった点は未解明のままであった。なぜなら、この解明には同じ構成相中で、組織形態だけを自在に変化させた材料を作製する必要があるからである。
本写真はこの解明を図1に示す「花状共晶組織」に着目することで、初めて実現したものである。この花状共晶組織は熱流方向に垂直にbcc-Ti相とB2-TiFe相からなる共晶組織を観察した際に見られるものであり、中心部の「おしべ」部分はロッド状、その周辺部は「花びらのように」放射状に板状組織が、数μmという極微細間隔で配列している。また興味深いことに、図2に示すようにこの組織は「形態によらず」いずれの部分でも両者に{112}bcc-Ti//{-1-1-2}B2-FeTi、<-111>bcc-Ti//<-111>B2-FeTi、という方位関係を維持していることがEBSD解析より確認された。
図3にはこの共晶合金の降伏強度の温度依存性を評価した結果を示している。評価は熱流方向に平行方向への圧縮試験により行った。この結果、本材料は室温で2GPaを超える著しい高強度を示しつつ塑性変形が可能であることが見出され、またさらに600℃の高温でも1GPa近い高強度を維持することから、新しい軽量耐熱材料として開発が今後強く期待できる。
本合金にてどのようにして延性が得られるのか、その塑性変形機構を解明すべく変形組織を観察したところ、図3(a、b)の光学顕微鏡像に見られるように、共晶組織を横切る「せん断帯」と、共晶組織が折れ曲がった「キンク帯」が試料中に観察された。この両者がどのような場所に形成されているのかを明らかにすべく、変形後試料中にて「せん断帯」、「キンク帯」が導入された部分を熱流方向に垂直にSEM-FIB法を用いて選択的に切断し、観察した結果を示したものが図3(c、d)である。この図から明らかなように、「せん断帯」はロッド状組織、一方「キンク帯」は放射状板状組織の部分に選択的に導入されることが同定された。この結果はまさにキンク帯の導入には「板状組織」の相互積層が必要であることを直接的、明快に示している。このような本合金での解析結果を基に、広くキンク帯による材料強化のための一般則・「ミルフィーユ条件」の理解が飛躍的に進み、今後の「ミルフィーユ型」新規構造材料開発に向けた重要な指針確立に至った。
学術的価値
本成果を基に「ミルフィーユ条件」が世界で初めて解明され、これまでにない高強度と延性を兼ね備えた新材料開発が飛躍的に進むことが特にAl合金やTi合金といった軽金属材料にて強く期待される。さらに、今回のロッド状組織においてはキンク帯が形成し得ないという結果を基に、これに層状にひずみ分布を与えることでキンクを導入する「拡張ミルフィーユ制御」という新概念の提案へと発展するなど、その波及効果は極めて大きい。
技術的価値
光学顕微鏡観察により、特有の「花状共晶組織」中の位置に依存して、構成相は同一であるにもかかわらず、組織形態に依存して異なる変形機構が発現する可能性が示唆されたが、その証明がこれまで困難であった。本写真の技術的価値は、今回、Gaイオンビームの条件等を適切に制御することで異なる変形機構が発現した場所の広範囲なFIB-SEM加工が可能になったことで、両者の相関を初めて直接的に明らかにできた点にある。
組織写真の価値
本研究の成功は図1に示すロッド状、放射状板状組織が組み合わされた「花状共晶組織」の存在により初めて実現され得たものであり、組織写真としても美しい様相を示す。さらにこの「花状組織の大きさ」がキンク帯の大きさを支配し、「一つ一つの花」が小さいほど細かなキンク帯の導入により合金が均一変形を示すようになることが明らかになった。すなわち、実際の植物と同様に、適切な「剪定」が機能発現の重要な要素となっている。
材料名
Ti-32.5 mass%Fe合金。この組成はTi-Fe二元系におけるbcc-Ti相とbccとB2型TiFe相との共晶組成に対応する。
試料作製法
ミルフィーユ組織制御には組織の配向が非常に重要となるため、本来であれば組織の配向制御にはブリッジマン法による一方向性凝固が望ましい。しかしながらTi-Fe合金は反応性が高いため、予備実験においてアルミナ、BNるつぼ等との反応を避けることが困難であった。そのため、本研究ではアーク溶解にてボタン状形態を有する合金を溶製した。アーク溶解は銅製のハースを用いて合金を溶製しており、ハース底部は水冷されているため、合金は常にハース底部から上部に向けて温度勾配が生じる。申請者らは、この温度勾配を利用して組織の配向を狙った。荷重軸方向が熱流方向と平行になるように、ボタン状試料の中央部から大きさ約1.5 mm×1.5 mm×4.5mm、もしくは1.2mm×1.2mm×3.0mmの角柱状の圧縮試験片を切り出し、真空中、室温から800℃の温度範囲にて圧縮試験を実施することで、「せん断帯」および「キンク帯」を試料内に導入した。
観察手法
圧縮変形後の試験片中の「せん断帯」および「キンク帯」が導入された部分をそれぞれ荷重軸方位に対し垂直に(すなわち、熱流方向に対し垂直に)複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)を用いて切断した。これにより図1に示す花状共晶組織中の、どの部分に「せん断帯」、「キンク帯」がそれぞれ形成しているのかを分離して観察することに成功した。FIB加工の際には、加工により変形組織の見え方が変化するのを防止するため、カーボン保護膜による保護を予め施し加工を行った。その後、得られた試料を60°傾斜させた状態でSEM観察することにより、図3に示す、荷重軸方位からの花状共晶組織と、荷重軸と90°をなす試料側面上に導入される変形組織との同時観察を実現した。
応募の内容は、上述のような高い学問的重要性が評価され、本年4月に以下の論文にて発表された。
T. Tokunaga, T. Yonemura, K. Hagihara, Materials Science and Engineering A, 900 (2024) pp.146505.
奨励賞
粒界を跨ぐ塑性すべり
応募部門
2.走査電子顕微鏡部門
応募者・共同研究者
1. 渋谷 陽二, 信州大学
2. 西川 幸次郎, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)
3. 松田 匠弥, 大阪大学
作品の説明
金属材料の塑性流動は、転位によるすべり変形に帰着される。多結晶材料の巨視的な塑性変形は、降伏後の変形初期では結晶粒内の転位源から射出される転位のすべりに基づくが、粒界近傍でのすべりの停滞と堆積が崩壊する臨界応力を超えると、粒界を跨ぐ塑性すべりが重畳される。このことが、巨視的な変形中期での加工硬化現象の主たる基礎メカニズムの一つと考えられる。その粒界を跨ぐ塑性挙動のメカニズムは金属組織学的、固体力学的にも多様な組み合わせの下での最小化原理で決定されるので、一般には観察が困難である。本応募の作品は、一つの結晶粒界とそれを介した2つの結晶粒から構成される長方形断面のマイクロメータサイズのピラー試験片を用いた単軸圧縮試験結果である。粒界エネルギーの大きな粒界では一般には自由体積が大きくなり、数個の転位は吸収される可能性が高い(参考文献:L. Li, L. Liu, Y. Shibutani, Mat. Trans., Vol. 65, 2024)。したがって、整合性が高く粒界エネルギーも極めて小さなシグマ(Σ)値3の双晶粒界を持つ無酸素銅の2結晶を電子線後方散乱回折法(EBSD)により選択し、集束イオンビーム(FIB)により多段階に加工された長方形断面のマイクロピラー試験片(断面約4μmx8μm、高さ約16m)を用いた。そして、フラット圧子を用いたナノインデンテーションにより準静的圧縮試験を実施した。ピラー体積を考慮すると内部の転位源はほぼ枯渇している一方、マイクロピラーの表面は転位源になることから、FIB加工により不規則に導入された表面ステップの任意な応力集中源から各結晶のシュミット因子に応じた転位が初期すべりとして射出される。エネルギー的に安定なΣ3双晶粒界での転位との反応の活性化障壁は大きいので(アルミニウムの参考値であるが、0.12eV/Å程度(T. Tsuru, Y. Shibutani, Y. Kaji, Phys. Rev. B, Vol. 79, 2009))、転位は吸収されずに堆積し、より作用応力の増大を伴う。2結晶と1粒界の結晶学的情報から求められる結晶粒界指数から(Y. Shibutani, T. Hirouchi, T. Tsuru, J. Solid. Mech, Mat. Eng., Vol. 7, 2013)、堆積した転位と粒界の反応と粒界からの射出を最小応力で許容するすべり系が選択され、その結果粒界を跨ぐ塑性すべりが達成される。これら一連の予想されるメカニズムを具現化し、実例として観察されたのが本作品である。従来より、多数のすべりが集合した金属材料における粒界を跨ぐすべりの観察(E. N.-Valeiras, E. Ganju, N. Chawla, J. LLorca, Acta Mat., Vol. 262, 2024等)や、イオン結合性材料における数個の転位と粒界の反応の観察(S. Kondo, T. Mitsuma, N. Shibata, and Y. Ikuhara, Science Adv., Vol. 2, 2016等)等はすでに報告されている。一般の構造材料における数個の転位の粒界を跨ぐ塑性すべりの観察はあまり例がなく、加えて、荷重ー変位曲線(公称応力ーひずみ曲線)における初期すべりの臨界応力とともに、その後の粒界を跨ぐ塑性すべりの生じる応力範囲を数値的に明らかにしていることも特筆すべき点として挙げられる。
学術的価値
表面ステップから転位が射出され、粒界での堆積によって作用応力が増大する。そして、結晶学的・力学的情報から求められる粒界指数に基づき転位と粒界の反応と粒界からの射出を最小応力で許容するすべり系の組み合わせが選択され、その結果粒界を跨ぐ塑性すべりが達成される。これら一連のメカニズムを具現化した新規性と、加工硬化を精緻にモデル化するための結晶塑性構成式の基礎データとして供与できる学術的波及効果を持つ。
技術的価値
粒界を跨ぐ塑性すべりを具現化するため、2結晶と1粒界の双結晶選択において結晶のすべり系を表す幾何学的方程式とともに、粒界指数を求める力学的方程式の連立した解を用いたこと。そして、その予測手法に基づくマイクロピラー作成方法を確立し、応力―ひずみ曲線における粒界を跨ぐ塑性すべりの臨界応力の推定を行なったこと。これら一連の過程に必要な転位の粒界を通過する限界荷重や変位の見極めが技術的価値を持つ。
組織写真の価値
本研究は、2013年度第64回金属組織写真賞走査電子顕微鏡部門奨励賞で受賞した円形断面のマイクロピラー試験片を用いた双結晶マイクロピラーの写真作品から始まった。マイクロピラーを用いた一連のメゾスコーピックな試験方法を確立し、粒界を跨ぐ塑性すべり挙動の観察への挑戦で得られた成果である。10年以上の試行錯誤の末、長方形型マイクロピラー試験片を用いた観察とその力学的評価を得たことに価値を持つ。
材料名
市場で流通しているJIS規格に準拠した無酸素銅(OFC、試験片サイズ:6mm×6mm×3mm)を焼鈍し、再結晶により結晶を肥大化させた試料
試料作製法
供試材は、(i)機械研磨工程、(ii)焼鈍工程、(iii)電解研磨工程の3段階で作成した。本研究は一般的な金属材料に見られる塑性すべりに着目し、その力学的な支配原理の探索を目的にしているので、試料としてはその力学挙動が得られやすい純度99.96%以上の無酸素銅(OFC)を用いた。また、本研究では1個の粒界を跨ぐ塑性すべりに着目しているので、a)周辺の粒界による力学的拘束を極力低減させること、b)粒内に存在する転位源と初期転位の存在をほぼ0にすることが求められる。したがって、結晶を再結晶によりある程度肥大化させるとともに、初期転位をほぼ消失させた。(i)機械研磨の手順は、耐水研磨紙で粗加工した後、酸化アルミニウム砥粒によるバフ研磨で仕上げ、アセトン浴で超音波洗浄後乾燥させた。(ii)焼鈍は、真空環境下で熱電対を用いた直接計測により炉内温度を制御し実施した。昇温速度は約100℃/minで、520℃で約600分焼鈍後炉冷した。その結果、平均結晶粒径は約50μmとなった。最後に、(iii)電解研磨は、電解液としてナイタール溶液を使用し、ドライアイスにより-35℃まで冷却したエタノール浴で行なった。再結晶された試料を、(i)EBSDにより適切な粒界と2結晶の組み合わせを選択し、(ii)FIBによるマイクロピラーの加工、そして(iii)ナノインデンテーションによる単軸圧縮変形の負荷を実施した。まず、(i)走査型電子顕微鏡(日本電子、JSM-IT100)に設置されたEBSD(TSLソリューションズ)により結晶粒の組み合わせを選択し、(ii)FIB(日本電子、JIB-4000)により、条件1(アパーチャー:270μm、プローブ電流10,000pA、ビーム直径330nm)で一辺の長さがナノインデンターの圧子直径20μm以上となるように粗加工を行った。その後、条件2(アパーチャー:60μm、プローブ電流320pA、ビーム直径60nm)を使用し、ステージを2度傾けて仕上げ加工することによりピラー傾斜の除去と修正を行った。マイクロピラーの高さと断面の寸法比は約2から3程度に設定し、ピラー根元の固定端による力学的拘束の影響を小さくした。そして、(iii)ナノインデンテーション(MTS、Nano Indenter G200)により、ひずみ速度5×10-4の準静的過程の単軸圧縮試験を行なった。
観察手法
適切な粒界を含む双結晶の抽出には、(i)粒界面の幾何学的配置の推定、(ii)2結晶のすべり系と各結晶粒のすべり面と粒界面との幾何学的関係性を含めた粒界指数の推定を行う必要がある。まず(i)については、対応傾角粒界で粒界面が平面であると仮定し、試料表面で観察される粒界の直線と試料側面と交差する直線の方程式から適合する平面の方程式を決定した(出典1))。そして、(ii)については各結晶粒のすべり系と粒界に関する(i)の結果を用いて、粒界を跨ぐ塑性すべりの容易さを表す指数としての粒界指数を計算した(出典2))。粒界指数が比較的小さい場合には、粒界を跨ぐ塑性すべり(転位の通過(transmission))の生じる可能性が低く、それぞれの結晶でのすべりが粒界面で会合する転位の結合(incorporation)による双結晶全体の塑性すべりとなる。これらの事象の起きる確率の大きな双結晶として4種類を選定した。その後、(iii)長方形型双結晶ピラーと、2結晶の正方形型単結晶ピラーを作成し、(iv)ナノインデンテーションより単軸圧縮試験を施した(出典3))。写真作品の図1に示したように双結晶としての公称応力―ひずみ曲線が得られ、図2のPillar4の双結晶ピラーを複数本用いてひずみ2.5%、4%、7%でのすべり系の解析をそれぞれ実施した。その結果、2.5%では各結晶粒でのシュミット因子(SF)の最も大きなすべり系(結晶Aはすべり系sp1(青色,SF=0.452)、結晶Bはすべり系sp1(赤色、SF=0.463))が活動し粒界で堆積していることが観察できた(図3参照)。ひずみ4%と7%では、各結晶粒のすべり系以外に、結晶Bから生じたすべり系sp2(緑色、SF=0.465)が粒界で堆積後、結晶Aに見られるすべり系sp2(黄色、SF=0.052)が粒界から発生していることが確認できた。このすべりの持つ結晶Aのシュミット因子(0.052)は極めて小さい一方、このすべり系の組み合わせに対する粒界指数が結晶Bでは1(最大値)、結晶粒Aでは0.833と極めて大きな値であることによると考察できる。図2のPillar1とPillar2では、各結晶粒の転位が粒界で堆積しそのまま双結晶としての塑性変形が継続したことから、粒界を跨ぐ転位の通過はなく、粒界での転位間の結合が生じたと分類できる。
出典:1)松田 匠弥,大阪大学工学部応用理工学科卒業論文,2021年度.
2)Y. Shibutani, T. Hirouchi, T. Tsuru, J. Solid Mech. & Mat. Eng., Vol. 7 (2013), pp. 571-584.
3)西川幸次郎,大阪大学工学部応用理工学科卒業論文,2023年度.
奨励賞
フェーズフィールドモデルに基づく画像処理によって実現された高速4D-CT観察
応募部門
4.顕微鏡関連部門
応募者・共同研究者
1. 鳴海 大翔, 京都大学
2. 下川 貴大, 京都大学
3. 中埜 創太, 京都大学
4. 勝部 涼司, 名古屋大学
5. 安田 秀幸, 京都大学
作品の説明
本作品は、TiB2添加Al-Cu合金の凝固過程における等軸晶のダイナミックな挙動を可視化した結果である。Al合金の鋳造において、TiB2を含む微細化剤は固相の不均一核生成サイトとして作用して等軸晶を形成する。等軸晶は、液相の流動や浮力により融液中を浮上あるいは沈降する。その際、等軸晶の成長による潜熱放出や溶質輸送を伴うため、等軸晶の運動は温度場や濃度場に影響する。また、等軸晶が堆積すると力を伝搬するネットワークが等軸晶間に形成されるため、外力が印加されると固液共存体特有の力学挙動が発現してせん断変形の局在化が起き、マクロ偏析や割れの形成に繋がる。すなわち、等軸晶の運動・堆積は結晶粒組織や鋳造欠陥の形成に関与している。しかし、凝固後の室温組織の観察のみから凝固過程の等軸晶の動態全てを把握することは困難である。
近年、可視光不透な金属合金の内部における凝固組織形成を現実の凝固プロセスに即した条件で時間分解その場観察できる手法として、大型放射光施設の硬X線領域の高輝度放射光を利用した時間分解X線トモグラフィー(4D-CT)が開発されている。4D-CTは、試料を180°回転する際に撮影された投影像データセットから時分割で画像再構成を行う手法であり、180°回転に要する時間が時間分解能の指標である。また、データセットの投影像の枚数が再構成像の質(空間分解能)に影響するため、時間分解能と空間分解能はトレードオフの関係にある。等軸晶の移動速度が101μm/sの場合、ボクセルサイズが10ミクロン程度の4D-CTでは、試料の回転は毎秒1周以上の速度が必要であるため、時間分解能の追求によって再構成像の質が低下する。さらに実用合金の多くは溶質濃度が低く、固液間のX線吸収コントラストが小さくなって再構成像の質の低下を招くため、固液のX線吸収コントラストが比較的大きなA-Cu合金でも実用合金組成において等軸晶の運動・堆積の定量評価は実現されてこなかった。
本研究では、フェーズフィールドモデルに基づいた画像処理により再構成像を復元させ、凝固組織形成の定量評価が可能な高速4D-CTを実現し、実用合金であるアルミニウム2000系合金の組成範囲であるAl-5mass%Cu合金等軸晶の成長および運動を捉えることに成功した。図1(a)がAl-5mass%Cu合金の凝固過程に撮影された再構成像であり、暗い領域と明るい領域はそれぞれ固相と液相である。再構成像の輝度の分布から等軸晶が存在することはわかるが、固液界面を正確にトレースするのは困難であり、三次元像を作成しても等軸晶を抽出できず、等軸晶の移動を追跡できない。図1(a)の固相率を拘束条件に、フェーズフィールド計算がその固相率に収束するような駆動力を与えて復元した画像が図1(b)に示されている。ノイズが除去されたことで固液界面形状やデンドライトアームが明瞭になっている。図2は、図1を含むデータセットから作成した三次元像である。画像処理によって三次元像から固相の抽出が可能となり、時分割のデータを用いて等軸晶が追跡できるようになったことが分かる。画像処理後に抽出した固相の時分割の三次元像を図3に示す。凝固初期は融液中に核生成した等軸晶が密度差によって沈降(速度: 50-150 μm/s)し、観察視野の下部に堆積して移動が停止した。堆積後に等軸晶間の液相において新たな等軸晶の核生成は確認されず、堆積した等軸晶の1次・2次アームが発達する様子が確認された。つまり、堆積した際の等軸晶の数と配置が凝固後組織の結晶粒サイズに対応することが実証された。
学術的価値
非常にダイナミックな現象である金属材料の凝固の動態をありのまま観察できるようになった。本研究で実現した観察手法を様々な冷却条件や組成の実用合金の凝固組織形成のその場観察に活用して定量データの蓄積を推進し「実際の凝固現象の見本市」が構築できると、凝固現象の実証的理解や理論体系の構築、組織形成シミュレーション・データ駆動型科学のベンチマークデータとしての活用といった波及効果が生まれる。
技術的価値
4D-CTの原理的に不可避である時間分解能の追求に伴う再構成像の劣化を、凝固・結晶成長シミュレーションで利用されるフェーズフィールドモデルに基づいた画像処理を施して復元した点に新規性がある。また、高温の金属凝固プロセスの高速4D-CT撮影が可能な独自の実験プラットフォームによって本研究を実現している。今後、更なる高速化が実現できれば、金属3Dプリンタ(AM)の凝固その場観察の実現も期待される。
組織写真の価値
凝固した後の室温組織からは評価できない等軸晶の運動を高速4D-CTによって可視化し、沈降速度や堆積後の結晶粒組織の形成に関する具体的な知見が得られた点で大きな意義がある。
材料名
Al-5mass%Ti-1mass%B合金(TiB2)を添加したAl-5mass%Cu合金
試料作製法
地金メーカーより入手した工業用純アルミニウムおよびAl-40mass%Cu合金地金を原料とし、黒鉛るつぼに充填して大気雰囲気の抵抗加熱炉中で溶解した。高純度Arガスを溶融合金(溶湯)にバブリングして脱ガス処理を行った後、Al-5mass%Ti-1mass%B合金を投入して十分に攪拌し、鋳鉄製の鋳型に注湯してインゴットを鋳造した。得られたインゴットから放電加工により直径0.8mm、長さ6mmの円柱状に加工して観察試料とした。観察時の試料容器には高純度アルミナチューブ(外径2.0 mm、内径0.8mm)を用いた。
観察手法
SPring-8のイメージングビームラインBL20B2の多層膜分光器で分光された40keVの単色光を用いて行った。試料が挿入されたアルミナチューブを真空チャンバー内の回転ステージに設置し、1Pa程度の真空中で加熱して試料を溶解した。試料を一周1sで回転させながら一定速度で冷却し、試料の透過像を撮影速度480Hz、ピクセルサイズ5.5μm x 5.5μmで撮影した。試料が半周する間に撮影した240枚の透過像(投影像)を用いて画像再構成を行った。時分割の再構成像に対してフェーズフィールドモデルに基づく画像処理を行い、ノイズが除去された固液界面形状を再構築した。この画像処理では、初めに再構成像の輝度の分布から固相率を算出し、その固相率にフェーズフィールド計算で得られる固相率が収束するようなパラメータを決定して固液界面を移動させる。その結果、曲率効果が界面の移動の駆動力としてノイズが除去される。画像処理の詳細については先行研究に記されている[H. Yasuda, T. Kawarasaki, Y. Tomiyori, Y. Kato, K. Morishita: IOP Conf. Ser.-Mater. Sci. Eng., 529(2019) 012023.]。
出典:オリジナル
応募作品
Observation of Stress-Induced Phase Transformations in Ultrahigh Toughness Zirconia Ceramics
応募部門
1.光学顕微鏡部門
応募者・共同研究者
1. オン フェイ シェン, 東京大学
2. 南部 洸太, 九州大学
3. 川村 謙太, 東ソー株式会社
4. 細井 浩平, 東ソー株式会社
5. 増田 紘士, 東京大学
6. 馮 斌, 東京大学
7. 松井 光二, 東京大学
8. 幾原 雄一, 東京大学
9. 吉田 英弘, 東京大学
作品の説明
Ceramics are renowned for their exceptional high-temperature and chemical stability, but their inherent brittleness limits their applications. To prevent catastrophic failure and broaden their use in structural components, enhancing toughness is crucial. Yttria-stabilized tetragonal zirconia ceramics, often referred to as "ceramic steel," are particularly notable for their stress-induced transformation toughening capability. When subjected to specific stress thresholds, partially stabilized tetragonal grains transform into monoclinic grains, which have a unit cell volume approximately 4% larger. This expansion generates a compressive strain field that effectively inhibits crack propagation. Importantly, toughness can be enhanced by decreasing the stability of the tetragonal phase through reduced dopant concentrations.
Recent advancements have shown that conventionally sintered 1.5 mol% yttria-stabilized zirconia (1.5YSZ), developed by Tosoh Corporation and the University of Tokyo, exhibits remarkable toughness—approximately four times greater than commonly used 3YSZ materials, as measured by the indentation fracture method. With the global push toward decarbonization, there is an urgent need for low-temperature, short-time sintering methods. Flash sintering presents a promising alternative, utilizing an electric field and current during the sintering process. Intense Joule heating is triggered by a specific combination of electric field strength and temperature, resulting in the instantaneous densification of powder compacts within seconds at significantly lower processing temperatures.
Figure 1 compares Vickers indentation imprints on near-full density samples of (a) 1.5YSZ and (b) 3YSZ, both produced via flash sintering at a furnace temperature of 1100°C for different durations, each within a total of 5 minutes. Magnified scanning electron microscopy images of a crack tip captured using secondary electron (SE) mode are presented in (c) and (d), while (e) and (f) show corresponding images obtained through backscatter electron (BSE) mode. Remarkably, the toughness of 1.5YSZ (KIC = 21.0 MPa·m0.5) is about four times higher than that of 3YSZ (KIC = 5.2 MPa·m0.5), comparable to samples produced through conventional sintering methods. The considerably shorter crack lengths in 1.5YSZ indicate that toughness enhancement is achieved through reduced yttria dopant concentration, lowering the threshold stress required to initiate the tetragonal-to-monoclinic (T→M) phase transformation. The increased number of transformed grains, evidenced by the extensive uplift of plate-like monoclinic variants surrounding the crack tip, leads to greater volume expansion that effectively suppresses crack propagation. Additionally, significant deformation from this volume expansion is suggested by rosette lines surrounding the indentation imprint (Fig. 1(a)), indicating that the deformation occurs in a non-elastic manner.
学術的価値
Near-full density 1.5YSZ samples were fabricated, achieving the highest toughness reported for flash-sintered zirconia, at a processing temperature reduced by 300°C and a processing time shortened from hours to minutes compared to conventional methods. The low yttria concentration facilitates the T→M phase transformation, enhancing toughness by suppressing crack propagation, as evidenced by symmetric rosette lines and minimally visible cracks around the Vickers indentation. This research sets a new benchmark for high-performance ceramics manufacturing.
技術的価値
Our approach enhances grain size uniformity in flash sintering by fine-tuning the current increment rate, enabling the fabrication of near-fully densified low-yttria-doped zirconia ceramics optimized for high toughness at lower temperatures and times. This method addresses microstructural inhomogeneity caused by unregulated Joule heating, particularly in 1.5YSZ, which risks cracking when grain sizes exceed certain thresholds. These advancements broaden the application of high-toughness ceramics while also supporting decarbonization efforts in manufacturing.
組織写真の価値
The reduction in crack length is closely related to both macroscopic features and the microstructure at the crack tips, which are vital for understanding the toughening mechanism. The exceptional toughness of 1.5YSZ stems from the increased volume expansion caused by a greater number of transformed grains, which effectively suppresses crack propagation. This relationship highlights the crucial role of microstructural analysis in developing tougher ceramic materials by elucidating how chemical composition and microstructure interact under mechanical stress.
材料名
1.5YSZ (TZ-PX-717N, Tosoh Corporation, Japan) and 3YSZ (TZ-3Y, Tosoh Corporation, Japan)
試料作製法
1.5YSZ and 3YSZ powders were cold isostatically pressed at 300 MPa into rectangular green bodies measuring 4.0 × 4.6 mm2 in cross-section. These green bodies, with a nominal electrode distance of 18.0 mm, were then flash sintered to achieve a relative density greater than 99% by applying an alternating current field at a furnace temperature of 1100°C in air. The 1.5YSZ sample was subjected to a maximum current density of 50 mA/mm2, while the 3YSZ sample reached a maximum current density of 100 mA/mm2. The current was ramped at a nominal rate of 0.5 mA/mm2·s, followed by a final holding time of 1 minute at the maximum current density.
観察手法
Optical images of the Vickers indentation imprint (load: 196 N) on the mirror-polished cross-section surface were captured using an optical microscope. The magnified microstructures around the crack tips, coated with a conductive osmium layer, were examined using a scanning electron microscope (JSM-7800F, JEOL, Japan) at an accelerating voltage of 5 kV and a working distance of 6.0 mm.
F.S. Ong, K. Nambu, K. Kawamura, K. Hosoi, H. Masuda, B. Feng, K. Matsui, Y. Ikuhara, and H. Yoshida. "Realizing near-full density monophasic tetragonal 1.5-mol% yttria-stabilized zirconia ceramics via current-ramp flash sintering." Acta Materialia (2024): 120496. (doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120496)
応募作品
電解コンデンサ用高純度アルミニウム箔に含まれる微量Pbの表面偏析
応募部門
2.走査電子顕微鏡部門
応募者・共同研究者
1. 大澤 伸夫, 株式会社UACJ
2. 冨野 麻衣, 株式会社UACJ
3. 林 知宏, 株式会社UACJ
4. 上田 薫, 株式会社UACJ
5. 本居 徹也, 株式会社UACJ
作品の説明
電解コンデンサ用高純度アルミニウム箔にppmオーダーで含まれるPbは立方体方位集積度を高めるための最終焼鈍工程で表面濃化する。Pb偏析サイトとピット形成の関係を明確にするため、低加速・高分解能FE-SEMとTEMを駆使し、微粒子で存在するPbの分布状態を広範囲で観察した。Pb微粒子はFE-SEMの1.7kV BSE像(反射電子像)を用い、AlとPbの原子番号の差によるコントラストで観察可能である(図1)。試料はPb含有量0.6ppmならびに5ppmの高純度アルミニウム軟質箔(厚み110μm)である。PbはBSE像で微粒子として圧延方向の隆起部に沿って多く分布する(図1(a)矢印)。Pb5ppmの箔の微粒子(図1(b)矢印)を加速電圧5kVでEDS分析するとPbが検出される。Pb 0.6ppmの箔表面の0.66kV SEM像を図2(a)に示す。表面は帯状の隆起部と平滑部が混在し、隆起部の一部(楕円枠)には亀裂が圧延方向に対して直角方向に生じている。30000倍のBSE像でPb微粒子を圧延方向に対し直角方向に連続して撮影し、得られた画像を図2(a)に重ね合わせた。Pb微粒子は隆起部と平滑部から成る表面形態に対応し、約30μmの周期で増減を繰り返す(図2(b))。FIB加工で得られたPb0.6ppmの箔の断面試料をTEM観察すると、図3(a)に示すようにアルミ素地とは異なる不均一な表面層(以下、表面酸化層)が観察され、EDS面分析で層状に酸素が検出される。Pb8.2ppmの箔の隆起部断面を圧延方向に対し直角方向にイオンミリング装置で加工すると、Pb微粒子が表面酸化層の亀裂近傍(図3(b))、層内の空隙ならびにアルミ素地と表面酸化層の界面(図3(c))に分布する様子がBSE像でとらえられる。Pb 0.6ppmの箔を用い、80℃、1mol/dm3塩酸-3mol/dm3硫酸の電解液中にて電流密度250mA/cm2の直流で15s間エッチングすると、図4(a)に示すように隆起部で溶解が進行し、平滑部の一部では溶解が遅延する。化成皮膜レプリカをSEM観察すると隆起部よりも平滑部のトンネルピット長さが短いことが分かる(図4(b))。このことはPb微粒子が多く存在する部分でアルミニウムの溶解が促進され、優先的にトンネルピットが成長することを示唆する。
学術的価値
アルミニウム表面に存在する表面酸化層は酸化を伴う微細加工組織と呼ぶことができ、その由来は熱間圧延時に圧延材から移着したアルミニウムとその酸化物が薄層状に堆積して生じたロールコーティングであることが本解析で示唆された。ロールコーティングが圧延表面に押し込まれる現象はピックアップインクルージョンと呼ばれ、圧延後の表面に形成された表面酸化層は最終焼鈍時にPbの集積サイトとなることが初めて明らかになった。
技術的価値
高容量化を目的とした工業的な製造プロセスの制御は材料メーカーにとっては重要な課題である。本解析で得られたPbの表面偏析挙動に関する知見に基づき、圧延表面のロールコーティングの制御によりピット分布の均一化が可能となり、長年の課題であったアルミニウム電解コンデンサの高容量・安定化を達成することができた。
組織写真の価値
機器分析装置に頼りがちであった材料解析に対し、改めて電子顕微鏡観察の重要性を示すことができ、電子顕微鏡観察こそが「木を見て森を知る」ための方法であることを証明することができたと自負している。得られた成果はアルミニウム圧延表面の本質を示し、前処理によるアルミニウム表面の表層除去やアルミニウム中に存在するPbのような微量元素の表面熱拡散挙動を考察する上でも多くの知見をもたらすものと期待される。
材料名
Si17ppm、Fe10ppm、Cu58ppmをベースとしたPb含有量0.6~8.2ppmの高圧電解コンデンサ用高純度アルミニウム箔
試料作製法
断面形態を観察するための試料はクロスセクションポリッシャ(日本電子製、SM-09010)および集束イオンビーム加工(JEM-9310)を用いて作製した。エッチング初期における箔のピット形態については85℃、0.8mol/dm3アジピン酸アンモニウム水溶液中にて電流密度50mA/cm2で40V化成処理後、アルミニウム素地のみをヨウ素−メタノール溶液中で溶解しトンネルピットのレプリカを作製した。なお、エッチングエリアの一部を予めポリエステルテープのマスキングによって被覆し、意図的にエッチング前の圧延目を残存させてトンネルピットの発生状況を調べた。
観察手法
断面加工した試料は低加速高分解能FE-SEM(Carl Zeiss製、ULTRA plus)とTEM(日本電子製、JEM-2010ならびにJEM-2100F)で電子顕微鏡観察した。Pb粒子の分布状態は低加速高分解能FE-SEMを用い、加速電圧1.7kVのBSE像にて観察した。トンネルピットの分布状態はレプリカ試料をSEM観察(日立ハイテク製SU8230)することにより調べた。
出典:N.Osawa,:MaterialsTransactions,65,p.825-836(2024).
N.Osawa,M.Tomino,T.Hayashi,K.Ueda,T.Motoi:J.Surf.Finish.Soc.Jpn.,50,p.504-511(2022).
応募作品
放射光X線マイクロトモグラフィによる無電解Ni-Pめっき7075-T6アルミニウム合金板の表層近傍に偏析する水素ミクロポアの観察
応募部門
4.顕微鏡関連部門
応募者・共同研究者
1. 堀川 敬太郎, 大阪大学
2. 日野 実, 広島工業大学
3. 星野 真人, 高輝度光科学研究センター
4. 上杉 健太朗, 高輝度光科学研究センター
作品の説明
7075-T6アルミニウム合金(Al-Zn-Mg-Cu系)の圧延板材から長手方向が圧延方向と垂直になるように試験片を切り出した。続いて試験片表面をエメリー紙研磨、脱脂、スマット処理、ジンケート処理(2回)を経て、85˚Cの無電解Ni-Pめっき浴に1.5h浸漬することで、厚さ8μmのNi-Pめっき膜(結晶質)を成膜した。大型放射光施設SPring-8のX線イメージングビームライン(BL20B2)において、X線マイクロトモグラフィ(μCT)を実施することで、材料内部の3次元組織を解析した。合金中に存在する空洞(ポア)は体積率で0.15%程度存在しており、圧延方向に配列することが明らかにされた。さらに、圧延板材の表面下層において、Ni-Pめっきのプロセスによって発生、吸蔵された水素を含むミクロポアの偏在が見られることが明らかにされた。なお、Ni-Pめっきを行わない場合では、この水素由来のミクロポアの偏在傾向はみられなかった。さらに、このミクロポアのNi-Pめっき下層での偏在は7075-T6アルミニウム合金の純度にも依存し、金属間化合物からなる晶出物を多く含む市販材純度の合金では、その傾向が高くなることを明らかにした。バルクの7075-T6合金内部におけるポアの空間分布をX線μCTで計測することによって、Ni-Pめっきによる水素で形成されるポアの形状、配向、偏在の状態をはじめて明らかにした。
学術的価値
アルミニウム合金に対する無電解Ni-Pめっきプロセスにより発生する水素によって、圧延板材の表層に水素由来の空洞欠陥(ポア)が生じることを明らかにした。この環境水素由来のポアはNi-Pめっきの下層の合金内部に偏在しており、さらに圧延方向への優先的な配向が見られることも明らかにした。このNi-Pめっき下層の水素欠陥の形成は、7075-T6合金中の不純物量にも影響を受けることなども明らかにした。
技術的価値
アルミニウム合金の無電解Ni-Pめっきのプロセスにおいて水素が発生することは広く知られていたが、発生した水素が合金内部に取り込まれ、どのような影響を与えるかは不明とされていた。本研究では無電解Ni-Pめっきで発生した水素によってアルミニウム合金板材の表層にNi-Pめっき由来の水素欠陥が発生することをX線μCTの技法ではじめて明らかにした。
組織写真の価値
無電解Ni-Pめっきによって発生した水素の一部が合金中に吸蔵されることでポアを形成することを明らかにした。めっき由来の水素によって生じる合金内部でのミクロポアが表層に偏析することをX線CTの透過レンダリング像を用いて可視化した内容に価値がある。
材料名
Al-5.5%Zn-2.6%Mg-1.6%Cu-0.28%Fe-0.21%Si合金(mass %)板材。表面に無電解Ni-Pめっき(低Pタイプ:1~2%P)を成膜。
試料作製法
7075-T6合金の圧延材を供試材として用いた。不純物Fe、Siを多く含む市販材ベース合金を用いた。試験片は冷間圧延の方向に対して垂直方向(T方向)になるように切り出した。試験片は半円切り欠きをもつ、最小幅1mm、厚さ1mmの試験片を用いた。熱処理としては溶体化処理(480℃、2h)、水冷後、人工時効120℃-24h(T6処理)を行った。無電解Ni-Pめっきの前処理として、試験片表面に付着した油分の除去を行うために、四ホウ酸二ナトリウム・十水和物を含む溶液を用いたクリーニングを行った。合金表面に形成されている酸化被膜の除去を行うための、水酸化ナトリウムを含む溶液を用いたエッチングを行った。エッチング時に生じたスマットを除去するために硝酸を含む溶液を用いた酸洗を行った。表面に酸化膜の形成をさせず、めっきとの密着性を上げるために、酸化亜鉛と水酸化ナトリウムを含む溶液を用いたジンケート処理(亜鉛置換)を行った。酸洗、ジンケート処理はそれぞれ2回ずつ行い、前処理とした(ダブルジンケート処理)。前処理後の無電解Ni-Pめっきとしては、皮膜のリンの含有量が1∼2wt.%の低リンタイプのめっき浴を用い、浴中に85℃で1.5時間浸漬させることで厚さ8μmのNi-Pめっき膜を作製した。
観察手法
試験片内部の3D構造は、SPring-8のBL20B2ビームラインを使用して、X線μCTで調査した。液体窒素で冷却されたSi (111) ダブルクリスタルモノクロメーターによって生成された光子エネルギー40keV、空間分解能780nmの単色X線ビームを試験片に照射した。CCDカメラを使用した画像検出器が試験片の90mm後方に配置され、試験台を180˚回転しながら1800枚の断層像を連続的に取得した。(露光時間:60ms/フレーム、3600フレーム/180°)。微細構造の二次元断面画像は、市販のレンダリングソフトウェア(Amira-3D、Thermo Fisher Scientific)を用いて三次元画像に変換した。
出典:International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 82, pp. 801–809
応募作品
Cu-0.03wt%P合金におけるデンドライト溶断過程の時間分解・その場観察
応募部門
4.顕微鏡関連部門
応募者・共同研究者
1. 小森 康平, 株式会社神戸製鋼所
2. 西村 友宏, 株式会社神戸製鋼所
3. 浦川 裕翔, 株式会社神戸製鋼所
4. 安田 秀幸, 京都大学
5. 鳴海 大翔, 京都大学
作品の説明
本写真は、放射光を用いた時間分解X線イメージングにより、Cu-0.03wt%P二元系合金(りん脱酸銅)の凝固過程を撮影した透過像である。本実験により、過冷凝固の際に初晶Cuのデンドライトが溶断する過程を観察した。
試料の大きさは10mm×10mm×0.1mmであり、観察領域は1mm×1mmである。透過像のピクセルサイズは、0.5μm×0.5μmである。試料全体が完全に溶融した状態からさらに20Kだけ温度を上げ、その後0.33K/sの一定速度で冷却し、凝固過程を毎秒5枚の時間分解で撮影した。また、観察領域の試料温度はほぼ均一である。各透過像の縮尺は同じである。
図1(a)は凝固開始直前で観察領域全体が液相である状態を0秒とした場合、そこから2秒経過し、0.7K程度温度が低下した透過像である。観察視野全体にデンドライトが成長していることが確認できた。なお、視野内にデンドライトが観察されてからの2次アームの成長速度は約11μm/sであった。
図1(b)は図1(a)から3秒経過し、1.0K程度温度が低下した透過像である。図1(b)で観察視野に成長したデンドライトの2次アームの成長速度は約7μm/sであった。成長速度が低下したことで2次アームおよび3次アームの粗大化により、デンドライトアームが一体化した様子が確認できた。
図1(c)は図1(b)から3秒経過し、1.0K程度温度が低下した透過像である。矢印で示すように、競合した2次アームの中で前方に成長した2次アームの根元が27μmまでくびれる様子が確認できた。さらに1.2秒経過した図1(d)では15μmまでくびれており、図1(d)から0.2秒後の図1(e)ではくびれ部で分断された。図1(f)で示すように、くびれ部の溶断により分離した固相は溶断後も曲率が大きいため、分断された両側は分断領域を拡張するように形状が変化した。
図2は矢印で示す2次アームの根元のくびれの直径および前方への先端成長速度の時間変化を示しており、図中に示す点線は図1の透過像取得時間に対応している。2次アームはまず前方へ成長するものの、成長の停滞とともに根元のくびれが進行していることが確認できた。また、根元での分断は分断直前に加速度的に生じていることをその場観察により明らかにした。
以上のように、過冷凝固によって形成したデンドライトが根元でくびれ、溶断する過程を時間分解でその場観察できた。
学術的価値
2次アームの溶断現象は既存のその場観察により明らかではあるが、実用合金よりも溶質濃度が高いモデル合金を対象としており、銅合金の観察もなかった。今回、溶質濃度が300ppmと低く、固相と液相のコントラストが小さく組織観察が難しい実用りん青銅合金の組成でも2次アームの溶断が生じることを実証した点は、今後の凝固シミュレーションのモデルなどへの応用が期待され学術的価値がある。
技術的価値
今回の観察に求められる技術課題は、1)1,200℃まで昇温可能な炉、2)X線を十分に透過し、0.1mmの液膜形状を保持できる試料セルと保持容器の材質、3)時間分解(5fps程度)で観察できるX線光学系、4)組織を明瞭にできる画像処理方法である。最も課題となったのは2)であり、液膜形状を保持するため材質に単結晶アルミナを用いた。
組織写真の価値
溶質濃度が300ppmである実用りん青銅合金において、過冷凝固の際の二次デンドライトアームの溶断の過程(デンドライト根元のくびれの過程)を時間分解で観察できた点に新規性がある。今回の写真では、室温での凝固組織観察では観察ができない2次デンドライトアームの溶断の時間変化で確認できた点で優れている。
材料名
組成はCu-0.03%P(wt%)であり、JISにおけるC1220に相当する汎用のりん脱酸銅である。
試料作製法
10mm×10mm×0.1mmの試料を作製した。10mm×10mmの中での厚さのばらつきは、0.1mm±20μm以内とした。厚さにばらつきがあると、試料溶融時に保持容器で均等に押さえることができないため、液膜状での保持が困難となる。クリープ変形を抑制できる単結晶アルミナ板(サファイヤ板)の試料セルにより、試料が溶融した際にも液膜状での形状保持が可能であった。
観察手法
凝固その場観察は、高輝度・高平行度な硬X線領域の単色光が利用できる大型放射光施設SPring-8のBL20B2のリング棟内の実験ハッチで実施した。試料サイズは10mm×10mm×0.1mmとし、試料に単色X線を入射し、透過したX線を可視光変換型のビームモニタを用いて透過像を撮影した。この時、凝固過程を観察するため、固相と液相の密度差による吸収コントラストを明瞭に観察できるよう、多層膜分光器で単色化した40keVのX線エネルギーで観察した。試料は真空チャンバー内で加熱し、発熱体はX線ビームが透過する部分に穴を開けたグラファイトヒータを用いた。観察領域は1mm×1mmであり、透過像のピクセルサイズは0.5μm×0.5μmとし、フレームレートは5fpsとした。なお、ビームモニタと試料の距離は炉からの輻射によって検出器にダメージが与えられないよう、0.5m∼1mとした。
出典:写真はオリジナルである。SPring-8のBL20B2にて撮影を実施した。