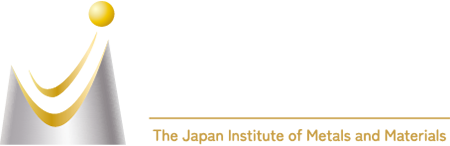2025年度活動中の研究会
本年3月から新たに下記のNo.89〜No.92研究会が発足いたします。
メンバーとして登録を希望される方は、氏名、勤務先、連絡先(E-mail address含む)を明記の上、世話人宛にお申込み下さい。研究会の活動期間は1期5ヶ年以内です。継続更新の場合は、延長期間1期3年以内、最長活動期間は2期8年以内です。
(研究会新設募集:7号会告予定/申請締切日/9月1日)
92.アモルファス合金・金属ガラスに関する研究会
【活動期間】1期5年間(2025年3月~2030年2月)
1970年代に急冷凝固リボン状アモルファス合金が、高強度・高靭性、優れた軟磁気特性や耐蝕性を呈することを世界に先駆けて示す等、我が国は、アモルファス合金研究をその黎明期から牽引し、学問の発展と産業化に大きく貢献した。1990年頃からは、過冷却液体の熱的安定化の学理を探求する、バルク金属ガラスの研究が我が国主導で開花した。近年、構造・組織やダイナミクスの解析法が飛躍的に進化し、稠密無秩序充填構造と考えられた金属ガラスにナノスケール不均質組織が内在することが示された。これがガラス形成・緩和といった物理現象や、マクロな諸性質に及ぼす影響を調べることで、金属ガラスの学理が深化を遂げ、新たな組織・性質制御プロセスの開発にも繋がっている。この研究の流れは、間もなくアモルファス合金もその対象として巻き込み、学問的融合を経て、新たな産業展開をもたらすと考えられる。この研究会は、産学官に跨る我が国の関連研究・開発者を集結し、世界に先だってこれに取り組むことで、アモルファス合金・金属ガラス研究およびその新たな産業化について、世界的イニシアティブを取り戻すことを目的する。
| 代表世話人 | 加藤 秀実 |
|---|---|
| 東北大学 教授 | |
| E-mail: hidemi.kato.b7[at]tohoku.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
91.格子欠陥基礎機能研究会
【活動期間】1期5年間(2025年3月~2030年2月)
格子欠陥は結晶性材料の合成・加工・利用の各段階において支配的役割を果たすだけでなく、個々の格子欠陥自身が電気伝導・熱伝導・光伝導など材料の機能的性質において局所的に大きな影響を及ぼす点で近年注目されている。これは最近の計測技術の向上により、従来不可能であった微小領域の計測が可能となり、かつ計算解析技術の向上の結果として現象の理解が深まったことと無関係ではない。今まさに、こうした格子欠陥の基礎的機能を再定義し、学問体系を再構築することが求められている。そこで、本研究会では格子欠陥の基礎的機能について最新の材料開発、高精度計測、高度な計算解析を通して、微小スケールからマクロスケールに至るまで、格子欠陥の機能を理解することを目的とする。
| 代表世話人 | 中村 篤智 |
|---|---|
| 大阪大学 教授 | |
| E-mail: a.nakamura.es[at]osaka-u.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
90.転位と力学特性に関するマルチスケール解析研究会
【活動期間】1期5年間(2025年3月~2030年2月)
これまで転位論を基盤として、材料の降伏挙動、加工硬化、破壊挙動など様々な力学特性が明らかとなってきている。転位一本一本の挙動については弾性論を基盤として多くのことが明らかにされているが、従来特異点として無視されてきた転位芯における溶質原子、特に水素や炭素と転位芯の相互作用や、転位の集団運動の結果として表れるマクロな力学特性との相関については、未解決の問題が多く残されている。一方、近年、計算科学や計測技術のめまぐるしい発展に伴って、これらメゾスケールにおける転位運動挙動と、マクロな力学特性との相関が徐々に明らかになってきている。山口珪次が刃状転位とほぼ同じ幾何的構造を有する塑性すべりのモデルを1929年に提案し、1934年にテイラー・オロワン・ポラニーらが結晶中の転位モデルを発表した。本研究会では、転位生誕100周年を見据えて、計算科学・実験科学のそれぞれ携わる研究者間での活発なディスカッションを通してメゾスケールでの力学特性とマクロスケールの力学的性質の発現メカニズムについての明確化を目的とすると供に、本分野の国際的プレゼンス向上を目指す。
| 代表世話人 | 田中 將己 |
|---|---|
| 九州大学 教授 | |
| E-mail: tanaka.masaki.760[at]m.kyushu-u.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
89.コンプレキシティ・トレランス研究会
【活動期間】1期5年間(2025年3月~2030年2月)
本研究会では、不純物を多く含むアルミニウム基やマグネシウム基、チタン基リサイクル地金の利用範囲拡大のための材料設計、材料組織制御、材料プロセスに関する指導原理として、新たにコンプレキシティ・トレランス(微視的組織やプロセス条件の階層的不均一性に基づいた損傷許容設計)を提案し、それらを基に実際の工業製品の製造時に安心してリサイクル地金が利用できることを実証することを目的とする。これまで工業用金属材料から取り除くべき存在であった不純物元素や介在物の影響・有害性を理解し、事前に製品や構造物の寿命を予測、設計上の留意点を喚起することで、リサイクル地金を構造材料として創造的再生、すなわち現時点のカスケードリサイクルを水平リサイクルに格上げするための新たな方策(学術変革)を提言することを目指している。
| 代表世話人 | 廣澤 渉一 |
|---|---|
| 横浜国立大学 教授 | |
| E-mail: hirosawa[at]ynu.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
88.高温構造用材料の水蒸気酸化に関する基礎科学研究会
【活動期間】1期5年間(2023年3月~2028年2月)
カーボンニュートラル(CN)の実現に向けて、耐熱金属材料を中心とした高温構造用材料の使用環境が多様化しており、これらの材料で生じる環境劣化を多角的な視点から議論する必要性が出てている。将来的に、アンモニアや水素が主な燃料となり、各種高温エネルギー変換プロセスのCNが実現する反面、排ガスの主成分である水蒸気による材料の酸化(高温水蒸気酸化)が顕著になることが予想される。金属材料の高温水蒸気酸化機構については、すでに定性的な説明がなされているものの未だ統一的見解がなく、水蒸気を含む多様な環境において包括的な議論ができていないのが現状である。また、水蒸気酸化により発生する水素が、母材の酸化挙動や諸特性に与える影響については全く検討されていない。そこで、申請研究会では、高温構造用材料における水蒸気酸化現象を多角的な視点から議論することで、現象の解明を目指すとともに、得られた知見から優れた耐環境特性を有する高温構造用材料の設計指針を提案する。
| 代表世話人 | 上田 光敏 |
|---|---|
| 北海道大学 准教授 | |
| TEL:011-706-6355 | |
| E-mail: mitsutoshi[at]eng.hokudai.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
87.水素が関わる材料科学の課題共有研究会
【活動期間】1期5年間(2023年3月~2028年2月)
近年の再生可能エネルギーの普及拡大に並行して、電力との相互変換が容易である水素エネルギーに対する期待は益々高まり、社会導入に向けた研究開発が多方面において進められている。さらに最近では、カーボンリサイクルに関連した諸化学反応に用いられる水素への需要も高まりつつある。水素エネルギーの製造・貯蔵・輸送・供給・利用のプロセスにおいて、各種機能性材料の利用への関心は高く、その研究開発は新規物質の創製から先端的手法による物性評価まで幅広い研究分野に渡って進められている。種々の専門分野を有する研究者それぞれが抱える課題を共有して情報交換および議論を行う場は重要であり、それらの課題解決を図ることで本分野の飛躍的な研究開発の進展が期待される。また、産官学の連携強化の機能も併せ持つことで研究開発成果を社会に活かしていくことができる。以上を鑑みて本研究会を企画する。
| 代表世話人 | 浅野 耕太 |
|---|---|
| 産業技術総合研究所 主任研究員 | |
| TEL:029-861-4485 | |
| E-mail: k.asano[at]aist.go.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
86.結晶性材料の結晶配向評価および結晶方位解析技術研究会
【活動期間】1期5年間(2022年3月1日~2027年2月28日)
結晶性材料の特性向上にあたり、結晶配向は重要な要素の1つである。さらには、材料における異方性および不均一性を考慮した最適な組織の作り込みが求められる。これらの結晶配向および材料組織の制御は、金属材料における単相組織のみならず、複相組織においても求められるものであり、さらにはセラミックス材料や結晶性高分子材料、複合材料においても同様に必要である。それゆえ、結晶方位の解析に基づいた配向・組織形成原理の理解が必須となっている。そのためには、最新の結晶方位解析技術による新たな知見の蓄積が求められるとともに、従来の結晶方位解析技術に基づいた集合組織評価法や結晶方位差によるひずみなどの厳密な取り扱い、配向・組織形成におけるシミュレーションなどを利用した定量的な理解についても重要さが増している。
本研究会では「結晶方位」をキーワードとした分野を越えた研究領域を対象として、金属、セラミックス、結晶性高分子を問わず結晶性材料における特性の向上を指向した研究活動を実施することを目的とする。
| 代表世話人 | 長谷川 誠 |
|---|---|
| 横浜国立大学大学院工学研究院 システムの創生部門 教授 | |
| TEL/FAX 045-339-3870 | |
| E-mail: hasegawa-makoto-zy[at]ynu.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
85.状態図・計算熱力学研究会
【活動期間】1期5年間(2021年3月~2026年2月) ホームページはこちら
様々な材料の機能を最大限に引き出すための組織制御において、状態図が果たしてきた役割はたいへん大きい。特に、状態図の熱力学的計算法であるCALPHAD法やマテリアルズ・インフォマティクスの提唱など、実験だけに依拠してきたこの分野の近年の研究環境の充実は目を見張るものがある。しかし一方で、状態図という基礎的で重要な研究領域を専門とする人材や、そこから生み出される研究成果のポテンシャルは年々低下の一途を辿っている。このような材料科学における基礎力の低下は、時間の経過とともに我が国における材料開発基盤や国際的競争力の低下をもたらすことは容易に想像ができる。そこで本研究会は、実測や熱力学理論に基づく精緻な状態図構築を通して、観察される現象の背後にある本質的学理を明らかにしながら、この分野の研究力の飛躍的な向上と人材育成、産業への応用を目指して設置するものである。
| 代表世話人 | 阿部 太一 |
|---|---|
| 物質・材料研究機構 主幹研究員 | |
| TEL 029-859-2628 | |
| E-mail: abe.taichi[at]nims.go.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
84.ソフト磁性研究会
【活動期間】1期5年間(2020年3月~2026年2月)
現在の軟磁性材料はケイ素鋼板、ソフトフェライトが多くを占めており、新たなソフト磁性材料の開発によるデバイスのさらなる高周波化や広帯域化、新規高周波磁気デバイスの創製が期待されている。ソフト磁性材料においては、これまで主として議論されてきたハード磁性材料と異なり、磁壁移動を始めとする磁化の動的挙動が磁気機能を支配する。
しかしながら、ソフト磁性材料の動作周波数領域での磁化の動的挙動は、磁壁移動、あるいは、渦電流によるエネルギー散逸のみで説明可能かなど、学術的にも不明な点が多い。すなわち、磁壁移動速度より高速、かつ、強磁性共鳴周波数には満たない周波数領域(数百 kHz から GHz 帯)での磁化の動的挙動を学術的見地から体系化することは、磁気物理の観点だけにとどまらず工学的応用の観点からも重要である。
本研究会では、上記の周波数領域における磁化の動的挙動を学術的に体系化し、ケイ素鋼板、ソフトフェライトに代わる新しいソフト磁性材料の開発指針を示すことを目指す。
| 代表世話人 | 遠藤 恭 |
|---|---|
| 東北大学大学院 工学研究科 准教授 | |
| TEL 022-795-3781 | |
| E-mail: endo[at]ecei.tohoku.ac.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |
83.高温材料の変形と破壊研究会
【活動期間】1期5年間(2020年3月~2026年2月)
世界的に、二酸化炭素排出量の削減が強く要請されている状況下で、発電プラントや輸送媒体の高温部では従来以上の高効率化が必須となっている。高効率発電・輸送媒体を支えるのは高温材料であり、その長寿命化や更なる高強度化のためには、変形、破壊および両者の関連性を基礎的な観点から改めて議論することが必要である。
高温材料の種類が多岐に渡っており、議論の場が細分化されていることから、できるだけ広い範囲の高温材料に関する知見を共有する場を作ることも求められている。特に若手研究者の人材育成という観点からもこのような場を提供することが重要である。
本研究会では、年1回の研究会を開催し、様々な材料における高温変形と破壊、また、高い力学特性を生みだす材料の内部組織に注目し、実験的ならびに計算的研究成果について基礎的な観点から討論し、高温材料の長寿命化・高強度化のための原理・原則を改めて見直すことにより、高温材料設計指針の再構築を目指す。
| 代表世話人 | 澤田 浩太 |
|---|---|
| 物質・材料研究機構 構造材料試験プラットフォーム長 | |
| TEL 029-859-2224 | |
| E-mail: sawada.kota[at]nims.go.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |