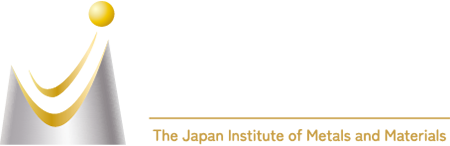2025年度新設「若手研究グループ」発足のお知らせ
若手および調査・研究事業を活性化することを狙いとして、若手主体の研究グループを発足しています。本年3月から新たに下記の研究会が発足いたしました。
10「構造材料とデータ科学の融合研究グループ」
活動期間:2025年3月1日~2027年2月28日の2年間
【設立の背景、必要性、目的、意義、得られる成果・目標等】
2021年に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション基本計画において、第5期基本計画で掲げたSociety 5.0を現実のものとすることが目指されている。Society5.0では「サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合」が提唱されており、その実現のために、特に材料科学の分野においては国が主体となって、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP、第1期:H26-H30、第2期:H30-R4、第3期:R5-R9)」や「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト(DxMT、R4.4-)」といった国家プロジェクトが実施されている。材料開発における「フィジカル」は多大な実験結果の集積であり、これをデータベースとみなす。そして「サイバー」は理論や情報工学であり、フィジカルであるデータベースと両輪を成すことで、これまで膨大な期間を要した材料開発の短期化や、データに埋もれていた新たな理論の発見に繋がる。
しかし、国家プロジェクトの性格上、若手研究者が研究を先導する機会は少なく、また一定の成果が求められる以上、自由な発想に基づく研究を行うことは難しい段階にある。さらに、自らの研究に情報工学的手法を取り込む必要性を感じつつも、理解が追いつかない、どのようなアプローチがあるのか単独で考えるには限界があるという声も聞こえてくる。
特に構造材料の分野においては、要求される力学特性や耐環境特性がますます厳しくなっていることから、その微細組織は複雑化の一途を辿っている。それに伴い、応力-ひずみ応答や破壊挙動、腐食、酸化挙動も単純な理論式では記述が不可能となり、組織と特性の関係性を一筋縄では解明できない状況にある。
このような状況において、データ解析に情報科学的手法を用いることにより、これまで単純には分離できなかった組織因子の抽出が可能となり、特性におよぼす組織因子の関係を階層的に明確化できる可能性がある。
今後10年、20年先の材料開発を見据えたとき、現在若手と呼ばれる人材が先頭に立ち研究を主導する立場になる。今この段階から情報科学を援用した材料開発手法について理解し、その考え方を深めることが、将来的にこれまで追求してきた実験的手法やアイデアに加え、「データサイエンス」をもう一つの武器として活かし、世界をリードする力を得ることに繋がる。
本若手研究会では、産官学において、これまで組織制御や力学特性、耐環境性といった構造材料に関する研究に従事してきた若手研究者と、情報工学を主たる手段として用いてきた若手研究者が一堂に会することによって、構造材料研究と情報工学を融合し、新たな研究テーマの開拓と学際的な協力体制の確立を目指す。また、若手研究者が主体となり、次世代の材料研究と技術革新を推進する。
新規研究テーマの開拓
構造材料と情報工学の融合によって、従来にはない研究テーマの創出を目指す。両分野の最前線で活躍する若手研究者が集まり、学際的なアプローチを推進するプラットフォームの形成を目指す。
学際的なネットワークの構築
異なる専門分野の研究者が一堂に会することにより新しい協力関係を生みだし、共同研究機会の創出を目指す。また、若手研究会にて得られた知見やアイデアを起点として、科学研究費助成事業への申請やその他外部資金の獲得を本研究会メンバーによる共同研究という形で実施する。若手研究会終了後には、得られた知見を総括し、さらなる学理の発展を目的に金属学会の「研究会」への申請を目標とする。
| 代表世話人 | 山形 遼介 |
|---|---|
| 千葉大学大学院工学研究院 | |
| E-mail: yamagata[at]chiba-u.jp | |
| ※[at]は@に変換して下さい。 |