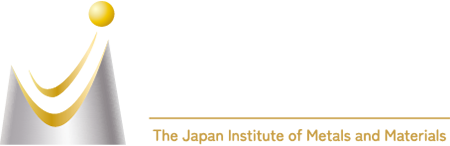イベントのご案内
第14回高校生・高専学生ポスター発表募集
申込締切日:2025年7月8日(火)
本会では最新の研究成果を発表・討議する場として毎年春秋2回の「講演大会」を開催しています。この講演大会では、若い生徒や学生に金属および材料学分野に対して興味や理解を高めてもらうため「高校生・高専学生ポスターセッション」を開催しています。2025年秋期講演大会では、2025年9月17日(水)に「北海道大学」で、9月25日(木)に「オンライン」で、「第14回高校生・高専学生ポスターセッション」を開催します。
発表者は、2025年9月17日(水)の現地発表または9月25日(木)のオンライン発表のいずれかで発表いただきます。
ポスターセッションでは、研究成果の発表を大学の教授や企業の研究者等の専門家に直接聞いてもらい、質疑応答が受けられる貴重な機会であり、さらにポスターの内容や発表の応答などを審査して、優秀な発表には会長による賞を授与します。金属および材料学分野に興味があり、本講演大会でポスター発表していただける生徒は奮ってご応募下さい。
発表者と指導教員は講演大会に無料で参加でき、研究者の最新の研究成果の発表を無料で聴講いただけます。詳細は、「高校生・高専学生ポスター発表要領」でご確認下さい。
加えて、9月17日に現地発表される発表者(連名の生徒さんを含む)と指導教員を対象に、今回から新たにランチョンセミナーを開催します。おいしいお弁当を食べながら、日本金属学会の活動内容を紹介します。さらに、ポスター会場に「缶バッジ作り」のブースを新たに用意しました。缶バッチ作りを通じて金属について一緒に学びませんか?
また、高校生・高専学生ポスター発表された方で希望者全員に、ユース会員の資格を贈ります。
「高校生・高専学生ポスター発表」要領
学会名:日本金属学会2025年秋期(第177回)講演大会
行事名:「第14回高校生・高専学生ポスター発表」
開催日時・方法:9月17日(水)午後 北海道大学現地発表 9月25日(水)午後 オンライン
対象者:高校生および3年以下の高専学生
発表方法:9月17日(水)現地発表または9月25日(木)オンライン発表のいずれか一方で発表
テーマ:材料に限定せず、フリーテーマです。(課題研究の成果、科学技術の取組等)
ポスター発表資料:作成要領は別途連絡
講演申込:https://www.jim.or.jp/convention/2025autumn
講演概要原稿:不要
参加要領(参加費および講演聴講、ランチョンセミナーへの参加)
① 発表者、共同研究者および指導教員の参加費を免除し、講演大会の発表を聴講できます。
② 希望があれば、高校生・高専学生ポスター発表の関係者(保護者、友人) 5名程度までの参加費を免除し、講演大会の発表を聴講することができます。
③ (現地開催の場合)指導教員は、事前に参加者リストを提出する。(別途用紙を送付予定)それをもとに参加証を作成し、現地でお渡しします。
④ 指導教員宛てに、参加者用IDとパスワードおよびプログラム1部を寄贈します。
⑤ 発表者全員に本会ユース会員の資格を贈呈します。
⑥ 昼食をとりながら、大学の先生のお話や学会についてお話が聞ける、ランチョンセミナー(無料、時間は11:30~12:30の予定)を開催いたしますので、ご参加頂きます。本ランチョンセミナーには、発表者、共同研究者、指導および発表関係者がご参加できます。なお旅程の都合でランチョンセミナーへ参加できない場合もポスター発表することは可能です。その場合は、申込の際に「備考欄」にその旨を記載頂くか、または事務局へ申込み締め切り日までにご連絡をお願いいたします。
⑦ ⑥の該当者は展示ブースにおいて、「缶バッジ作り」を体験できます。
優秀ポスター賞:優秀な発表には日本金属学会長賞、最優秀ポスター賞および優秀ポスター賞を授賞します。
問合せ・連絡先:
(公社)日本金属学会 講演大会係
〒980-8544 仙台市青葉区一番町 1-14-32
TEL:022-223-3685
FAX:022-223-6312
E-mail: annualm jimm.jp
jimm.jp
オンライン発表でのリスクについての注意
下記の注意事項をご確認の上で講演のお申込みをお願いいたします。
講演大会での発表には、現地開催、オンライン開催にかかわらず、以下のようなリスクがあります。特にオンライン開催では、密室から参加することが可能で講演会場のような衆人監視が行われないこと、および講演がWeb 上で配信されることから、これらのリスクが高まることが懸念されます。本会では、リスクを低減するために、考えうる対策を取りますが、最後は参加者のモラルに訴えざるを得ません。これらを理解の上、十分に注意して講演の申し込み及び発表をしていただきますようお願いいたします。
〈発表に伴うリスク〉
1. 研究情報を不正に取得される
不正聴講、講演の録画・録音・撮影(スクリーンショットを含む)が行われてしまう
※パスワード発行によって参加者を限定するとともに、録画・録音・撮影等の禁止を周知徹底しますが、最終的には参加者にモラルを守っていただくことになります。
※本大会で使用するオンライン会議ツールでは録画機能は使えません。
2. 著作権を侵害してしまう
他人が著作権を持つ音声、映像、画像、写真の安易な使用(引用)により、著作権を侵害してしまう
※文献などはこれまでの講演大会と同様、適切な引用がされていれば問題ありません