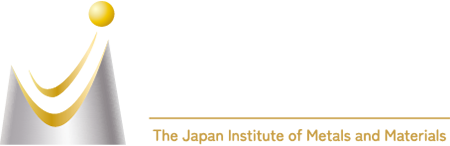イベントのご案内
2026年春期講演大会公募シンポジウムテーマ要旨
2026年春期講演大会では、下記3テーマの公募シンポジウムを実施します。講演を申込む場合は、希望するシンポジウムを選択して申込下さい。
S1 高温材料の変形と破壊
Deformation and fracture of high temperature materials
世界的に、二酸化炭素排出量の削減が強く要請されている状況下で、発電プラントや輸送媒体の高温部では従来以上の高効率化が必須となっている。高効率発電・輸送媒体を支えるのは高温材料であり、その長寿命化や更なる高強度化のためには、変形、破壊および両者の関連性を基礎的な観点から改めて議論することが必要である。本シンポジウムでは、2020年度~2025年度まで行った「高温材料の変形と破壊」研究会の総括を行い、 様々な材料における高温変形と破壊、また、高い力学特性を生みだす材料の内部組織に注目し、実験的ならびに計算的研究成果について基礎的な観点から討論する。
テーマ責任者
(シンポジウムchair):物質・材料研究機構 グループリーダー 澤田 浩太
(シンポジウムco-chairs):富山県立大 鈴木 真由美、北大 池田 賢一、東北大 関戸 信彰、名大 高田 尚記、九大 光原 昌寿
S2 特異反応場における時間/空間応答を利用した新奇材料構造創成 VIII
Tailoring of novel-structured materials using spatio-temporal responses under exotic reaction fields VIII
非平衡状態を利用したナノ・マイクロ組織を有する材料の開発や物性探索では、極限反応場や特殊環境下の非平衡励起状態、緩和過程に代表される時間変化を利用した*エキゾチックな*時間的・空間的応答の理解・制御が重要である。同趣旨にて開催した過去7回のシンポジウムでは2件の基調講演に加え、常に15件程度の一般講演があった。このように会員の興味が高いことを踏まえ、2026年春期講演大会でも継続開催する。基調講演としてエキシマレーザー光を使った材料表面改質の最新研究成果に加えて、生体材料に対して高エネルギー線が与える影響及びその利用による治療技術への応用について発表して頂き、特異反応場での時間/空間応答を利用したナノ・マイクロ組織形成過程の広い理解につなげる。加えて特異反応場をキーワードとする一般講演も交えて新規材料開発に向けた課題などを討論する。
テーマ責任者
(シンポジウムchair):筑波大学数理物質系物質工学域准教授 谷本 久典
(シンポジウムco-chairs):東北大 森戸 春彦、(株)illuminus、中村 貴宏、大阪公立大 堀 史説、岩瀬 彰宏
S3 データ創出・活用による磁性材料の研究開発 III
Digital Transformation Initiative R&D for Magnetic Materials III
マテリアルズ・インフォマティクスの世界的潮流から10年以上が経過し、データ駆動型材料研究が産学官に浸透するとともに、研究手法が飛躍的に進展している。基盤技術としては、自動・自律実験、網羅計算、生成AIなどが進展し、それらのマテリアル応用に注目が集まっている。一方、適用事例が増えるにつれ、他分野の動向を把握することが困難になっている。このような背景のもと、文科省・データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト(DxMT)では、対象材料系の異なる5拠点がデータ駆動・DX 研究を推進し、データ連携部会において拠点間の連携がなされている。
本シンポジウムでは、磁性材料に主要ターゲットの一つとするが、構造材料等の多様な材料系を含め、データ駆動手法・DXを活用した材料開発の現状と課題を議論する。産業界における先端研究事例、DxMTの磁性材料、構造材料拠点における取り組み、アカデミアからの最新の成果を含め、国内外の社会実装、産業振興に資する、幅広い材料への展開も見据えた広範なデータ創出・活用型材料研究の発表と活発な討論、情報交換を期待する。
テーマ責任者
(シンポジウムchair):産業技術総合研究所研究センター長 三宅 隆
(シンポジウムco-chairs):NIMS 大久保 忠勝、東北大 宮本 吾郎、岡本 聡、NIMS 袖山 慶太郎、只野 央将、産総研 岡田 周祐